静岡大学、EVのサイドポッドは「箱」から「翼」へ【学生フォーミュラ2025・空力観測 第2回】
前回から数回にわたって掲載する予定の「空力観測」。学生フォーミュラ日本大会2025で、気になった空力部品にフォーカスしていく。前回は立命館大学のシャークフィンに着目した(リンク:立命館大学、奇抜なシャークフィンに見る実証主義的な姿勢【学生フォーミュラ2025・空力観測 第1回】)。今回は、さらに特徴的な形状の空力部品を紹介したい。静岡大学のサイドポッドだ。アンダーカットというには凹んだ位置が高く、さらに深く鋭い。むしろ「2段構造」と表現するほうが適切かもしれない。このサイドポッドを初めて目にしたのは、8月のエコパ合同テスト。その時はまだ下地塗装のみで、それが特異な形状をより強調していたようにも思う。大会に現れたマシンは鮮やかなオレンジに塗装され、異彩を放つサイドポッドは、意外にもマシンの一部として美しく収まっていた。


このサイドポッドは、上下2段で明確に役割が分かれている。下段(三日月形状の中)は車体下を流れる気流を利用し、地面効果によってダウンフォースを生み出す形状だ。一方、上段は整流を目的としており、上側ではフロントウイングで持ち上げられた気流を受け止め、リアウイングへと導く。そして、上段の後方、黒く塗られた部分がパワートレイン冷却用のダクトだ。もともと冷却ダクトは存在しなかったが、試走を重ねるうちに冷却能力の強化が必要となり、鳥人間コンテストチームの協力を得て追加設計されたものだという。内部にはブラインド状のフィンが多数配置され、パワートレインに向かって均一に分散するよう工夫されている。この精巧な仕組みが、限られた空間での冷却と空力の両立を実現している。フロアはカーボン積層による高剛性構造、サイドポッドは発泡材を削り出して樹脂で固めたもの。材料選択にも、軽量化と加工性を両立させる知恵が光る。


学生フォーミュラにおけるサイドポッドは、ICVとEVで少し異なる。ICVではラジエータが収まるだけでなく、チームによっては排気系、特に高温になるエキゾーストマニホールドやサイレンサーを配置するための空間としても機能している。そのため内部温度が高く、サイドポッドは“熱との戦いの場”だったのだ。一方、EVでは排気系という制約がなくなる。モーターやインバータ、バッテリの冷却経路を比較的自由に配置できるため、サイドポッドは空力的な発想で形を決められるようになった。つまり、熱を逃がすための「箱」から、空気を操る「翼」へと進化している。静岡大学のサイドポッドは、その違いを体現している。
サイドの空力部品は車両中央に近く、前後バランスを崩さずにダウンフォースを得られるというメリットはあるが、その設計はやっかいな領域だ。フロントウイングからの流れ、タイヤ周りの乱れ、そして後方にはリアサスペンションやリアタイヤがある。ある学生フォーミュラの空力設計者は、「サイドでダウンフォースを稼ぐコンセプトの場合、フロントウイングと連携する必要がある」「計算リソースがあって、同じ担当者が数年かけて開発しないと難しい領域」「サイドの開発に力を入れているチームは、3〜4年同じ設計者が担当しているところもある」と語る。

フォーミュラEを見てもわかるように、EVの空力開発はエンジン吸気や排気経路といった制約がなくなり、車体外形の自由度が格段に高まっている。静岡大学のマシンは、EV開発を進める中でその領域に大きな一手を講じてきたといえるだろう。先に述べたとおり、効果を得るにはなかなか難しい領域ではあるが、EVのメリットを最大限に生かした、機能美の光るマシンへとさらに進化していくことに期待したい。
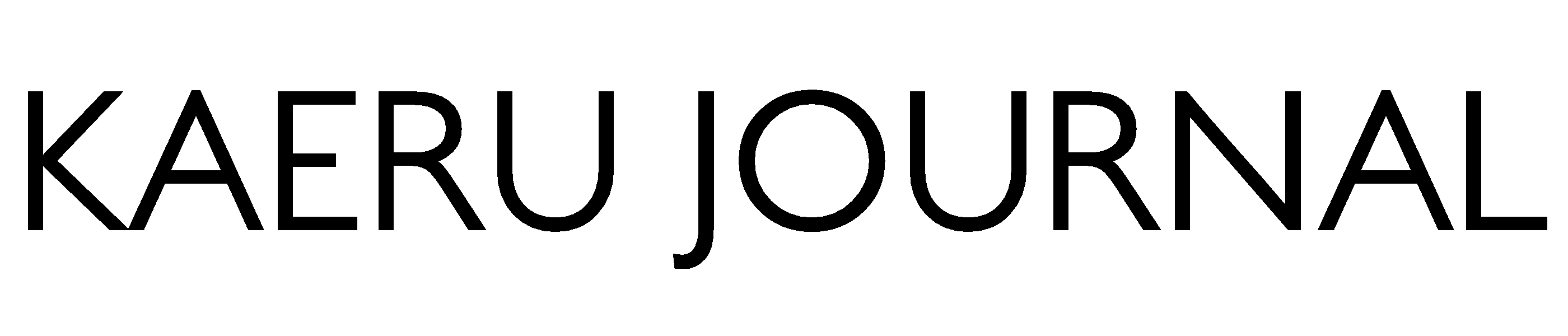


“静岡大学、EVのサイドポッドは「箱」から「翼」へ【学生フォーミュラ2025・空力観測 第2回】” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。