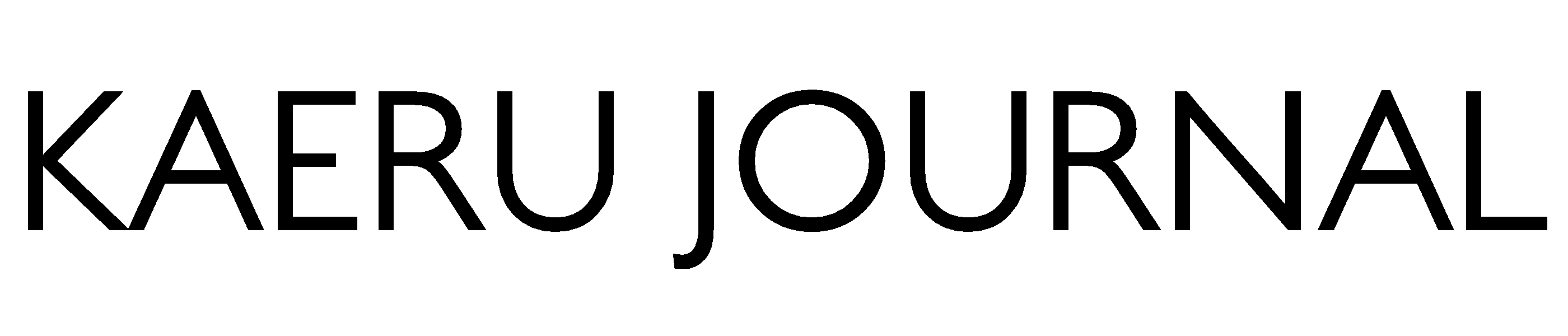2026年大会まであと1年、前倒しの影響は?各チームの準備状況【学生フォーミュラ】
学生フォーミュラ日本大会は例年9月に開催されてきたが、2026年大会は会場の都合により、異例の8月開催となる。(公式通知:第24回学生フォーミュラ日本大会2026 会場・会期についてのお知らせ)これにより、各チームの年間スケジュールにも大きな影響が生じる。新体制への移行、設計・製作スケジュールの前倒し、そして大会時期前倒しに対する特別措置の“Second Year Vehicles”(前年のマシンを継続使用する選択)の検討など、各チームが取る戦略はさまざまだ。今回はいくつかのチームに2026年大会に向けた準備状況について聞いた。



Aチーム
すでにモノコックやレイアウトの設計に着手しているAチームは、新車開発を前提に動いている。
「ローカルルールでSES(静的審査資料)の解釈が変わると詰んじゃうので、新車を作る前提でいる」と語るように、大会仕様への適合性を重視する姿勢がうかがえる。一方で、「流用するのはすぐできるから準備だけはしておいて、間に合わなければSecond Year Vehiclesを適用する」と柔軟な選択肢も用意している。部品の設計では「今年の部品が使えるようにはしていく」とし、現行マシンとの互換性も意識して開発を進めている。
Bチーム
年間のマイルストーン全てを1ヶ月前倒す考えのBチーム。「もう動き出して、部品の割り振りなども決めている」「設計期間も走行期間も全部1ヶ月前倒しする予定」で、「走行期間が夏休みより前に来るため厳しいところもあるが、リードタイムを減らさないようにする」という姿勢。1年生にも早期にベンチマークの経験を積ませるなど、チーム全体に“前倒しモード”を浸透させている。
Cチーム
Cチームでは、2026年の新リーダーが決定したばかりで、慎重に次年度の構想を練っている段階だ。
「考えとしては、極力新しい部品を担当メンバーを作らないようにする」と語るように、今年の設計担当が翌年も同じ部品を担当する方針を取っており、引き継ぎによる遅れを最小限に抑えようとしている。また、「1回生にはスケジュールに大きく影響しない部品」を担当させることで、開発の安定性を確保しつつ、人材育成の機会も設けている。「このシーズンに蓄えられるものは蓄えて2027年大会に備えても行きたい」と中長期の視点も忘れていない。
Dチーム
Dチームは、「Second Year Vehiclesは考えていなくて、新しいこともやろうとしている」と語り、完全新車の開発に向けて意欲的だ。
「エンジン、サスペンションなど大きく手を入れていく可能性もある」と技術的な挑戦も視野に入れるが、スケジュール面では「どこで1ヶ月を短縮するのが良いかのスケジュール感が一番難しい」と迷いもある。設計、製作、走行、いずれの期間を削るかによってチーム運営に与える影響は大きく、慎重な判断が求められている。
Eチーム
2026年に世代交代を控えるEチームは、「今年のマイレージや速さ次第ではSecond Year Vehiclesも考えている」と語るなど、現行マシンの活用を含めた柔軟な戦略を取っている。
「車体は作り直したとしても、今年の部品が付くような設計にはしたい」と、部品の再利用性を意識しつつ、「今年のうちに速いマシンのベースを作って来年後輩たちが見失わないようにしたい」と語るように、2026年を“育成と移行”の年と位置づけている。



前例のないスケジュール変更は、すべてのチームにとって不確定要素を孕むが、それぞれが独自の判断と柔軟性をもって対応しようとしている。Second Year Vehiclesという保険を持ちながらも、新車開発への意欲を失わない姿勢が、多くのチームに共通している。1ヶ月早まった舞台に向けた“最適解”を、各チームがどう見出していくのか注目される。