立命館大学、奇抜なシャークフィンに見る実証主義的な姿勢【学生フォーミュラ2025・空力観測 第1回】
10年前と比べると、エアロ部門はパワートレインやサスペンションと並びチームを構成する主要な開発部隊の1つになっている。学生フォーミュラをやりたいという学生たちからの人気も高い。その多くが、いかに効率よくダウンフォースを得るか、という課題に向き合うわけだが、今年の立命館大学はそれとは異なるアプローチを見せた。彼らはフロントウイングもリアウイングも排し、シャークフィンのみを搭載したマシンで今シーズンの戦いに臨んでいる。

チームによると、その背景にはチームとして抱えてきた疑問があるという。「元々エアロがある方が速いという根拠(シミュレーションや実測結果)がチームとして無かった」。この一言に、彼らの開発方針が端的に表れている。データに裏づけられた根拠がなければ採用しないという、実証主義的な姿勢である。
昨年の大会での経験も、今年の決断に大きく影響した。昨年のオートクロスの1本目ではエアロを装着したが、フロントウイングが路面に干渉するトラブルが発生。2本目ではフロントウイングを外し、さらにエンデュランスではエアロをすべて取り外して走行した。その結果、「タイムがそんなに変わらなかった」という意外な事実が判明。「あっても無くてもタイムが変わらないなら、壊すリスクなどを考えて付けないという判断を今年はした」。この判断は、単なる簡略化ではない。リスクとリターンを冷静に天秤にかけた結果であり、規定の中で最大の性能を引き出すというエンジニアリングの原点を体現している。

では、なぜウイングを完全に廃してシャークフィンを残したのか。「今年は、ウイングは付けないが、エアロ開発自体はする。何か他と違う面白い事をしたいと思って付けた」と語る。シャークフィンはF1マシンなどで見られるような強力なダウンフォースデバイスではない。しかし、その存在は明確な空力的意味を持つ。チームはシャークフィンの効果を検証するため、ドライバーコメントに加えてタフト(糸による気流観察)を用いた実測も実施した。ドライバーからは「そんなに変わらない」という感想があったが、タフトを貼って走行したところ、コーナリング時の気流変化が明確に確認された。そのため、チームは継続して採用することを決定、大会にもその状態で臨んでいる。

狙いは「直進安定性」だろう。メインフープの後ろ、縦方向に配置されたフィンは、ヨー方向の安定性を高める働きを持つ。高速走行時やコーナリングでのヨーイング発生時に、車体側面の気流を整え、ヨーを抑える方向に作用する。大型リアウイングの翼端板が同様の役割を果たすことを考えれば、その効果は理解しやすい。シャークフィンはダウンフォースを稼ぐ装置ではなく、空力バランスを整え、ドライバーが安心してアクセルを踏み込める環境を生み出す装備と言える。 多くのチームが強力なダウンフォースを狙うウイング全盛の学生フォーミュラ界にあって、立命館大学のシャークフィンは異彩を放つ。彼らのアプローチは、エアロダイナミクス開発において、単に力を生む装置としての追求ではなく、車両全体の運動特性、操縦性、リスクマネジメントまでを包含する総合的な視点の重要性を示している。
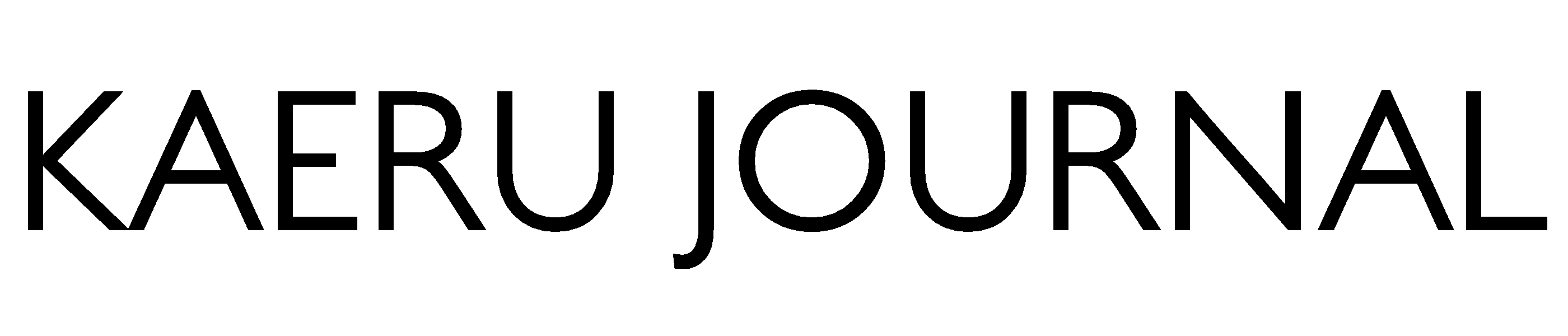


“立命館大学、奇抜なシャークフィンに見る実証主義的な姿勢【学生フォーミュラ2025・空力観測 第1回】” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。