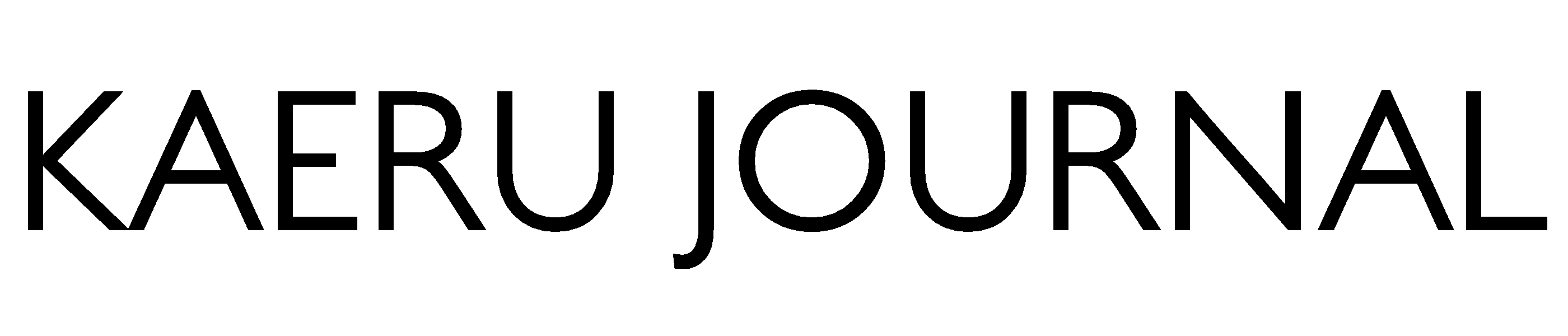続々と走るニューマシン、シェイクダウンから見るチームの『バイタル』は良好か【岡山大学】
2025年4月6日、2025年マシンをシェイクダウンする岡山大学学生フォーミュラプロジェクトを訪れた。ガレージに到着すると、チームは最終ミーティングの最中であり、学内道路を封鎖してマシンを走行させるためのオペレーションを入念に確認していた。ミーティング終了後、バリケード用のタイヤやパイロンの運搬、ドライバー装備の準備、ガレージからのマシン搬出など、チームは一連の作業を淀みなく進めていた。走行場所とマシンの準備が完了し、いよいよドライバーがコクピットへ。単気筒エンジンを搭載するマシンは、エンジン始動に若干時間を要したものの、程なくして始動。ドライバーは慎重に発進し、40~50mほど走行したところでマシンを停止させシェイクダウンを完了した。その後、シフトリンケージやウイング等細かなトラブルに対処しながら、複数のドライバーが交代でストップ&ゴーを繰り返していた。走った瞬間にチームから歓声が湧くでも無く、思いの外あっさりとしたシェイクダウンからはチームにとって予定通り進んだことが読み取れた。チームリーダーは「今年軽量化にかなり力をいれていて、その成果も数値で確認出来て、無事シェイクダウンが出来てまずは一安心」「ウイングも今年新しく作ったもので、企業さんの作業場所を借りて製作した」「自立(サスペンション組付)は1日遅れだったが、シェイクダウンは予定通り出来た」と話した。



学生フォーミュラ大会事務局が公開している一般的なチームスケジュール(リンク:スケジュールマネージメント)を参照すると、シェイクダウンの時期は6月末頃に設定されている。それと比較すれば、5月上旬、ゴールデンウィークを迎える頃のシェイクダウンでも十分に早いと言える。ましてや、3月や4月という早い時期にシェイクダウンを行うことは、プロジェクトが相当に前倒しで進行しているという印象だった。『だった』という過去形が示すように、かつては早期のシェイクダウンは稀であったが、近年はその傾向が強まっている。昨年の実績を見ると、東北大学は2月下旬、大阪大学は3月上旬にシェイクダウンを完了させている。そして今年、鳥取大学は2月中旬、大阪工業大学は3月下旬、岡山大学は4月上旬にそれぞれシェイクダウンを実施した。このように、早期にシェイクダウンを行い、実際に走行可能な状態のマシンを準備する最大の理由は、走行テストの時間を確保しマシンの信頼性を高めること、その先にはエンデュランス完走が見据えられていると考えられる。それに加えて、講義の少ない春休みの期間を最大限に活用して製作を一気に進めたい、静的審査に向けた準備に時間を割くために、マシン製作を早期に完了させたいという意図も考えられる。

逆にチームがハマりやすいケースがある。4月以降に新学期が始まり、授業の合間に製作を進める場合、どうしても作業の進捗は遅れがちになる。ゴールデンウィーク以降の6月にまでシェイクダウンがずれ込むと、静的審査の書類作成などの準備に追われ、マシン製作が一時的にストップしてしまう可能性もある。6月に静的審査の書類を提出した後、製作を再開し、7月にようやくシェイクダウンを迎えることができたとしても、車検対応でマシンに修正が必要となる場合があり、大会本番までの走行可能期間は8月のわずか1ヶ月程度となることも少なくない。このような状況では、信頼性の確認や修正、セッティングの煮詰めが十分にできず、結果として大会で本来のパフォーマンスを発揮できないチームも散見される。これらの事例を考慮すると、早期に製作を進め、走行可能な状態のマシンを手に入れることは、年間を通じたプロジェクトの成否を左右する重要な要素と言える。しかしながら、「今年からシェイクダウンの時期を2ヶ月前倒ししよう」と簡単に計画できるものではない。昨年の東北大学は、前年のフレームを改良して使用することで製作期間を大幅に短縮している。また、大阪大学も既存の部品を積極的に流用することで、早期のシェイクダウンを実現している。一方で、7月や8月にシェイクダウンを迎えても、入念な準備とテストによって大会で優秀な成績を収めているチームも存在するため、単に時期が早ければ良いというわけではないことも理解しておく必要がある。
肝要なのは、チームが掲げる目標を達成するために、いつまでにどのような状態のマシンでシェイクダウンを行う必要があるのかを明確に定義し、その計画を着実に実行することである。そうして策定されたシェイクダウン日程をしっかりと守れるチームであれば、自ずとチーム全体の目標達成への道筋が見えてくる。実際に、早期シェイクダウンを成功させた東北大学と大阪大学は、いずれもそれぞれのチームが設定した目標を達成している。この事実から見ても、シェイクダウンの時期やマシンの完成度を観察することで、その年のチームの勢いや組織としての動きをある程度予測することができると言えるだろう。



改めて岡山大学の事例に目を向けると、彼らが早期にマシンを走行させたのは、未完成な暫定仕様を無理やり走らせたという印象は全くない。チームが綿密に計画したスケジュールに沿ってマシンは着実に製作され、空力デバイスであるウイングもしっかりと搭載されていた。そして、冒頭で述べたように、マシンを安全かつ効率的に走行させるためのオペレーションも洗練されていた。これらの要素から判断するに、岡山大学の学生フォーミュラプロジェクトは非常に良好な状態にあると言える。逆に、そういう状態のチームでなければ計画通りに完成度高くシェイクダウンを迎えることが難しいだろう。同様に、早期にシェイクダウンを成功させている鳥取大学や大阪工業大学も、良好に準備が進んでいると推察されるこれからシェイクダウンをするニューマシンとともに、チームの動きも注視していきたい。