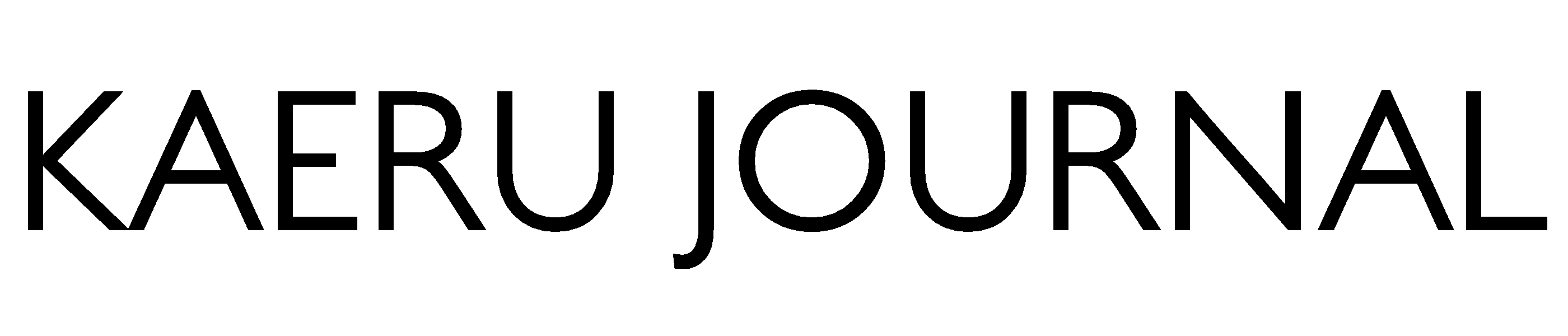関東でもEVが存在感を示す、工学院がトップタイム死守もその差は僅か0.3秒【茂木合同テスト】
7月6日、モビリティリゾートもてぎ南コースで、HONDA主催の合同テストが開催された。コースは大会のエンデュランスレイアウトをベースに、南コース全体を使った専用レイアウトが用意され、関東勢の工学院大学や上智大学に加え、東北大学も参加した。天候は晴れ。昼過ぎには一時的に雲が厚くなり雨粒が落ちる場面もあったが、路面が濡れることはなく、終始ドライコンディションでの走行が続いた。路面温度は、前週の泉大津テストと同様、9時にはすでに40℃を超え、すぐに50℃に達した。人にもタイヤにもマシンにも厳しい、タフなテスト環境となった。
会場には前日から入り、コース設営と半日の走行を行っていた工学院は、マシンとドライバーの準備を手際よく進め、周回走行に進んだ。快音を響かせながら走り出したマシンは、リアの接地感を保ちつつ旋回していく様子から、これまでの工学院の流れを継承しているように見えた。ただ、実際にはトラクション側やコンバイン領域でのスタビリティが不足していた模様。これに対しチームはLSDのイニシャルトルクを調整し、加えてアンチロールバーの効果も確認したという。ドライバーは「持ち込みの状態だと、トラクション抜けが感じられた」「立ち上がりにかけてヨーが収束する前にどんどんアクセルを踏んでいって、ゼロカウンターで立ち上がりたいのにリアが砕けてしまって滑ってしまっていた」「ストレート前の2コーナーや立ち上がりや、Mコーナーの最後の方で滑るようなことが多かった」「これに対してデフとリアスタビを試した」「デフだけでも効果は感じられたが、もう少し改善しないかと思ってスタビもやってみた」「最終的にはリアが踏ん張るようになって、今日の課題は解決出来たかと思う」と振り返った。また、『今年のパワートレイン』については「低速のトルクが太くなって、(コース)後半のセクションは乗りやすくなった」「今のところネガは感じていないが、適合を進めて行く必要はある」と評価していた。なお、前日から使用したタイヤは終盤には構造が浮き出るほど摩耗しており、特にフロントの摩耗が目立っていた。それでもこの日のトップタイムを死守し、71.3秒でテストを締めくくった。



一方、1日を通じて最も動きがあったのは東京大学だった。今年のマシンは大幅な仕様変更が加えられており、バッテリー配置の見直しに加え、フロントタイヤは10インチ化、リアサスペンションはリジットからダブルウィッシュボーンへと変更された。フロント10インチ、リア13インチという異径なタイヤ構成もあり、見た目のインパクトとともに、ライバルたちの関心を集めた。結果は、速かった。もちろんこれは、この日の工学院に対する立ち位置と挙動を見ての感想だが、それで事足りるほどの驚きがあった。今季HFDP with B-Max Racing TeamからFIA-F4選手権に参戦するドライバーの新原は「昨年までの違いでいくと、トルクがすごい出せるようになったことが一番の違い」「モーターの性能としてはあるが、バッテリーの電流が足りなかったり、駆動軸が弱くてモーターの力に耐えられないということがあったが、チームがそれらの課題を解消してくれてやっとモーターの限界まで使えるようになった」「特にストレート前の2コーナーからの加速が今まで乗った車の中で一番良くて、F4と比べ物にならないくらい良くて楽しかった」「車体としてもそのパワーを受け止めるだけの性能を感じている」「EVで車が重いというのはあるが、思い通りに操れるポテンシャルがあると思う」「(スラロームの動きが大きく変わることがあったが)制御の問題もあると思うが、ドライビングを試していることのほうが多かった」「トルクが出るようになって、プッシュアンダーが出やすくなっている」「そこはトルクベクタリングを使いながら改善していきたい」「去年よりは確実に良い結果が出せると思う」とポジティブな手応えを語った。タイムも好調で、この日は71.6秒をマークし、2番手につけた。



3番手には日本工業大学が入った。「茂木の合同テストといえば日工大」と言ってもいいほど、毎年印象に残る走りを見せる日工大は、前後にウイングを装着しないシンプルなマシンで今年も好タイムを記録した。今年は当初、エンジンの変更を計画していたものの、設計進捗とスケジュールを踏まえて昨年と同様のPC44Eを搭載。ただし搭載位置を下げ、低重心化が図られている。その効果もあってか、これまでバネ上の動きがやや大きく接地感にばらつきがあった挙動が、今年はスムーズで「ひらひら感」が増していた。コースクローズ間際、路面温度が40℃台に下がったタイミングでアタックしたドライバーは「持ち込んだ状態での課題としてはステアリングの重さ」「フロントの内圧を変更して試したところ改善されて、ドライバーのフィーリングも良くなった」「去年はマージンを取っていたが、今年はエンジンの高さを下げた」「その低重心化が効いていると思う」「(タイムについて)かなり運動性能は上がっていると思う」「ここから乗りやすくなるように調整を進めていきたい」「今日一日同じタイヤを使っているが、熱ダレはあるものの摩耗による落ちは感じていない」と手応えを語った。記録したタイムは72.3秒で、工学院に1秒差まで迫る内容だった。2023年のオートクロスのリザルトと比較しても、大きく差を縮めてきた印象だ。ウイングレス車両最速を狙う日工大だが、ウイング装着車も視界に入るほどの進化を見せた。



そのほか、上智大学や東北大学などのEV勢も積極的に周回を重ね、トラブルシュートやセットアップに取り組んでいた。新たにSENTURYタイヤを投入した日本大学理工学部は74.3秒を記録。路面温度的にはタイヤの性能レンジに入っていた印象だが、真のポテンシャルを引き出すには、さらなる調整が必要と見られる。