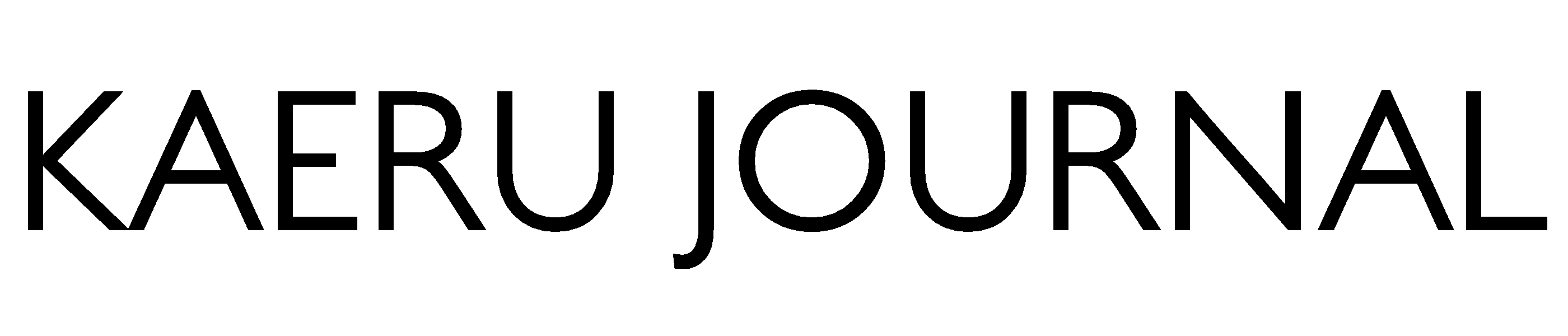13インチから10インチへ、変化する足元事情
東京都市大学チームの場合
「一言でいえば、13インチではオーバーサイズだった」とメンバーが話す東京都市大学チームは2018年に10インチに変更。「これまでのマシンは軽量化が進んでいなくて、13インチが妥当だったが(車重が)200kg付近まで軽量化された現在のマシンでは10インチが妥当」とも語る。
本来、タイヤはその負担荷重に応じて適切な空気量、すなわちサイズが決まり、骨格剛性や各部ゴム素材の設計もそこから進められる。ましてレースタイヤでは設定荷重(各輪あたりの車両重量はもちろん、最近の準レーシングマシンでは空力荷重も加えたものになる)に応じて変形、路面との摩擦による発熱、そこで現れるトレッド・コンパウンドの軟化〜粘着状態が発生するように造られている。その設定範囲よりも荷重が少なすぎると、トレッド面の温度が上がらずに本来の粘着状態にならず、硬いままのコンパウンドを削って走るのに近い状況になる。つまり、本来の“グリップ”を引き出すことが難しい。ちなみに荷重が大きすぎる場合は、車両の質量とそこに加わる運動による慣性力を受け止めきれないので、これは競技車両でも一般車でも論外である。従前、日本の学生フォーミュラ設計者が10インチ・タイヤの選択を躊躇してきたのは、その不安によるところが大きかったのではないか。最近の車両諸元検討・設計の進化の中で、都市大は軽量化された車重に適合する設定荷重(もちろん1輪あたり)のタイヤを選ぶと10インチになった、ということだろう。
プロフェッショナル・レースではタイヤメーカーから各チームに使用するタイヤ特性を示した「タイヤデータ」が提供され、チームはこのタイヤデータを参照しタイヤ内圧やサスペンション・セッティングの“適合”を進める。同様に学生フォーミュラにも「タイヤデータ」が存在する。正式にはFormula SAE Tire Test Consortium(TTC)という組織によって共有される試験データで、2004年当時、ニューヨーク州立大学バッファロー校の博士だったEdward M. Kasprzak氏を中心とするメンバーがボランティアで始めたものだ。学生フォーミュラで使用が想定される複数のメーカーのタイヤをフラットベルト試験機を使って基本的な特性計測を行った結果が提供される。当初はMilliken Research Associates, Inc.が試験装置と計測実務を提供、そのコスト(超割引額)をデータを希望したチーム群が負担する、という形で始まったものだという(その概要についてはFSAE Tire Test Consortium < https://www.millikenresearch.com/fsaettc.html > ご参照。成り立ちや初期のデータのあらましについては2006年にSAEで発表した講演要旨< https://pdfs.semanticscholar.org/3a2b/ecff7142121f4b25d88082c19d837422f305.pdf > を一読されたい)。2005年から2018年までに6メーカー・41種類のタイヤをテストしている。日本でも多くのチームがこのタイヤデータを入手、参照してマシン設計を進めている。都市大もこの基礎データから13インチではオーバーサイズと判断したのだ。
そこで10インチ化の課題についても聞いてみた。一番に挙げられたのは、13インチに比べて小さくなるホイールリム内のレイアウト。「理想と考えるサスペンション・ジオメトリーを実現するためにホイール内側ギリギリまでアームを持ってくる必要があった。シェイクダウンの時点では干渉が発生し、その部位をヤスリで削った」という。さらに「Aアームの開き角やナックルアーム長(車軸からタイロッド取り付け点までの距離)次第では(アーム、ロッドも)干渉する」。これらの課題に取り組み都市大は10kg以上の軽量化に成功したという。

機械加工後のアップライトを比較する。下部片側だけ腕部(ナックルアーム)が張り出しているのが前輪用、下部両側にピボットが張り出しているのが後輪用。上が2019年の10インチ・ホイール車両、下が2017年の13インチ・ホイール車両のもの。中央のハブベアリングのための円のサイズが大きく変わっていないことを考えると、アップライトの上下寸法が大きく短縮されたことは一目瞭然。 (写真は全て同チーム提供。チーム(Mi-Tech Racing)のウェブサイトは< https://www.mitech-racing.com/ >)
10インチ化には軽量化に加えてコンパウンドの温度上昇・粘着力発生の発動の早さ、というメリットもあると予想されるが、都市大チームはこの点について「発熱、摩耗は明らかに10インチのほうが早かったと思う。新品一発目がいちばん良く、そこからあるところまでグリップが下がって、ある程度の距離までは落ちたところのグリップが維持される。その(新品のグリップが)落ちる点は10インチのほうが早い」と、発動の早さとともにグリップダウン、摩耗の早さも体感として得られたようだ。
学生フォーミュラについてあまりご存じでない読者の方々に向けて簡単に紹介しておくなら、このイベントにおける動的審査、つまり自分たちが作った車両を実際に走らせてそのタイムを競う競技は、直線0-75mを走る「アクセラレーション」、定常円をつないだ8の字状のコースを周回する「スキッドパッド」、カーブやスラロームが連続するコース1周のタイムアタックを行う「オートクロス」、同様のコースを約20Kmにわたって走る「エンデュランス」の4種目だ。エンデュランス以外は各種目ドライバー2名まで出走が可能で1名につき2アタック・計4回のアタック機会が与えられ、その中のべストタイムで競う。エンデュランスはオートクロスとほぼ同じレイアウトのコースを2名のドライバーが途中交代して走り抜く。日本大会では1周約1kmをそれぞれ10周ずつ、計20周を走行しトータルタイムと燃費を競う。現在の日本大会の競技フォーマットでは5日間にわたる日程の中で、前半は静的審査、3日目にオートクロス、スキッドパッド、アクセラレーションの3種目が行われ、4日目と5日目にエンデュランスが行われる。そしてこのエンデュランスの出走順はオートクロスの結果によって、そのタイム・ランキングの遅い方から順に出走し、オートクロスでトップタイムを出したチームが最後に出走するというパターンに落ち着いている。
じつはこの出走順が、エンデュランスで速く走るための鍵のひとつなのだ。数十台が同じコースを走るため、出走順の最初と最後では路面の埃や砂、そして路面に付着するトレッド・ラバー(同種のコンパウンドであれば、ある程度付着した状態のほうが粘着力が高くなる)などのコンディションに大きな差が出る。天候が安定していて路面が濡れなければ、という条件付きだが、エンデュランス出走順が後になるほど、つまりはオートクロスの順位が良いほど、きれいでグリップの良い路面コンディションを得やすいことになる。これはエンデュランスのトータルタイムはもちろん、その中の1周のファステストタイムを狙う上位チームにとっては重要な要素だ。
エンデュランスで最善のコンディションを得るためにも、オートクロスで速く走ることが求められるわけだが、そこで重要になってくるのが、都市大チームも体験したタイヤの発動の早さだ。学生フォーミュラの競技はいずれも、タイヤは冷えた(外気温程度)状態からすぐにアタックランに入る。サーキット・レースの予選のように、決められた時間の中でまずウォームアップ走行を何周かして、タイヤを発動させた(トレッド・コンパウンドの温度を上げて粘着状態にした)ところでアタックするということができない。そのため1人のドライバーが2回出走する中で1本目は確実にタイムを残しつつタイヤの準備に使い、スタート地点に戻って(順番待ちの待機はあるが)2本目に本命のアタックを行う、という作戦を採るチームが多く、ここでタイヤの発動の早さが重要になってくるのだ。速さのトップを競うチームでは「前後の(グリップの)発動バランスが悪い、アタックラップ後半で後ろ(のグリップ)が落ちてフルアタックができなくなる」という声が聞こえるほどシビアな状況になりつつある。ただし、発動が早まる一方で都市大チームが経験したように摩耗も早まるため、エンデュランスの中でどうタイヤを保たせるかも今後の課題になってくるだろう。
東京農工大学チームの場合
都市大チーム同様、2018年に10インチ化を試みたがその年は設計が対応しきれず断念、翌年の2019年に10インチ化を果たしたのが東京農工大学チーム。こちらは10インチ化の動機を「ライバル(の4気筒勢)が10インチにしているのでトレンドに乗った」と話す。使用するコンパウンドやリム幅も多くのチームで使われているものを選択したとか。また上位チームが毎年新規にアップライトを設計製作する中、農工大はここ5年ほど同じアップライトとハブを継続して使用しており、それらを新しくするタイミングとも合致して10インチ化を決断したという。
農工大チームのシャシー担当者は「とりあえず走らせることを優先して、ジオメトリーは基本的に13インチの値のままとしたが、(シャシー性能は)結果的におかしなところにはいなかった。先輩たちの設計が良いところにいたと思う」と話す。ドライバーも「トラブルで多くは乗れていないものの、(タイヤ、ばね下の)路面追従性は上がっている印象。大会(オートクロス)のタイムからあと1秒は上がるポテンシャルを感じている」と好評価だ。ただ、今後については後輩たちに委ねていると前置きをしつつ、「アッカーマン・ジオメトリーの設定、操舵系については検討の余地を多く残している」「路面追従性についても効果の検証が必要な要素だ」と10インチ化したマシンへの理解を深める必要性を感じている様子だ。
農工大チームも都市大チームと同じく10kg程度の軽量化を実現できたようだが、同年に初めて前後にウイングを搭載したことでその軽量化分は相殺。結果的に車両重量は前年度と同程度になったとか。 また大会後この10インチ化された農工大のマシンに乗った2019年総合優勝チーム・名古屋工業大学のエースドライバーは、「フロントは良く応答していてピーキーすぎるほど。ステアリングギア比(が高い)かなという気がする。スキッドパッドはかなりきれいに旋回していて、あとはバランスかな。(10インチ・タイヤで走って選定した)内圧設定も違和感はなかった」とコメントしており、課題は残すものの10インチ・マシンのベースとしては成功と言えそうだ。